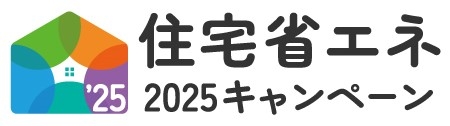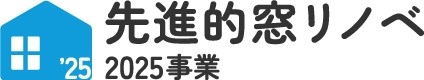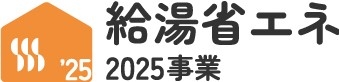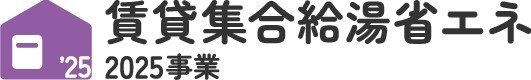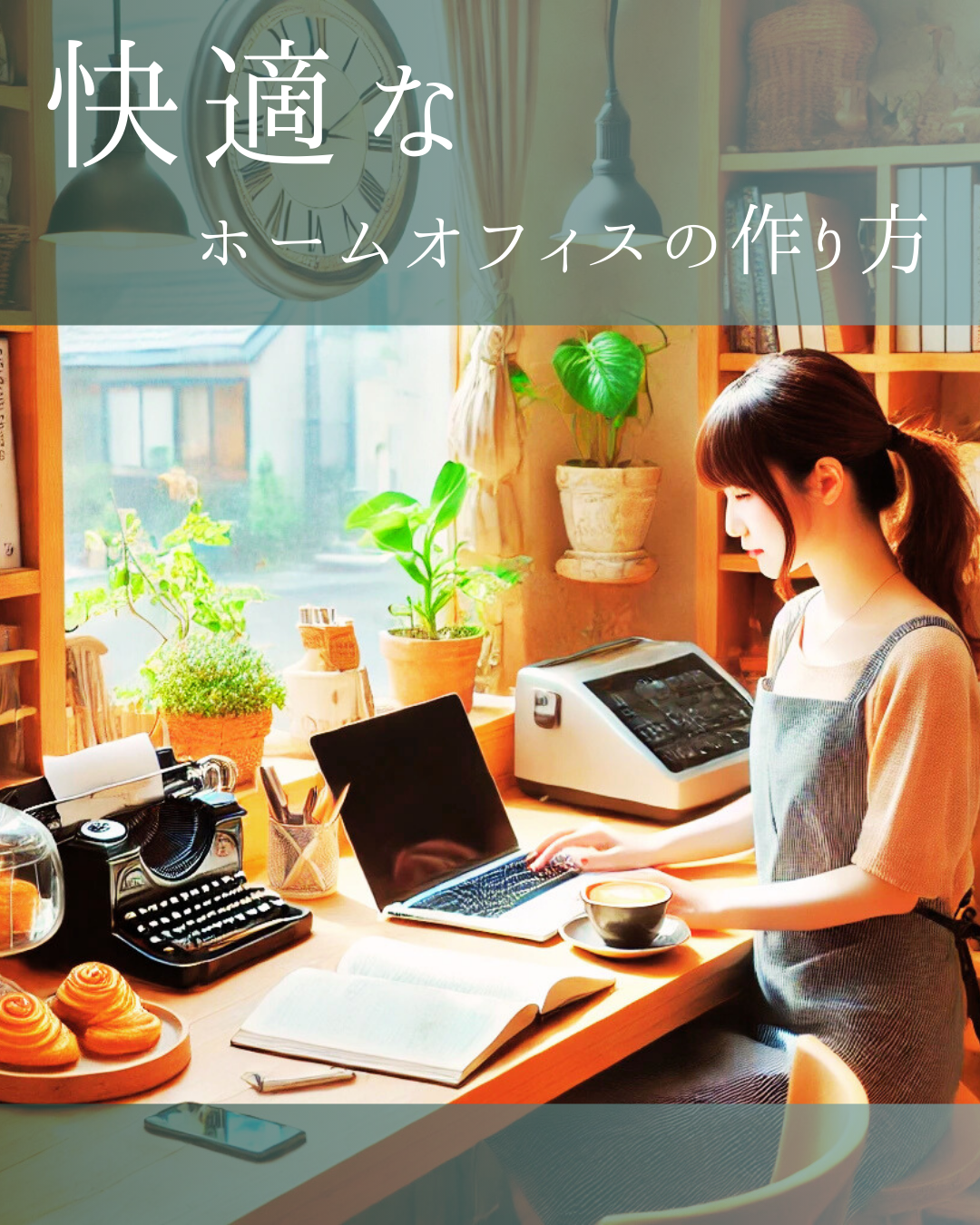(有)Y&M企画工房 2025年の補助金制度紹介します
皆様、いつもお世話になっております
(有)Y&M企画工房 石神 昂貴です
お客様皆様に朗報があります。
弊社(有)Y&M企画工房は
去年に引き続き住宅省エネ支援事業者となっておりますのでご報告させて頂きます
「住宅省エネ支援事業者」とは何か?
ある補助金制度を受ける事の出来る事業者の事で
その補助金制度内の各事業の補助対象である
住宅の建築・販売、リフォーム工事等を行う事業者となります。
お客様の代わり、各事業の交付申請等の手続き等も行います。
住宅省エネ支援事業者情報
(有)Y&M企画工房
登録事業者番号
S099091
となっております。
 又、先程からお話させて頂いている
又、先程からお話させて頂いている
ある補助金制度も紹介させていただきます
その補助金制度とは...
[住宅省エネ2025キャンペーン]
「住宅省エネ2025キャンペーン」とは?
「住宅省エネ2025キャンペーン」は、
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、
家庭部門の省エネを強力に推進するため、
住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の
住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の事です。
住宅省エネ2025キャンペーンの4つの補助事業ってなんだろう?
1.子育てグリーン住宅支援事業
新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、
「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、
2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、
既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業
2.先進的窓リノベ2025事業
既存住宅の早期の省エネ化を図り、エネルギー費用負担の軽減及び住まいの快適性の向上と、
2030年度の家庭部門からのCO2排出量66%削減、「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現に
貢献するとともに、先進的な断熱窓の導入加速により、価格低減を促進することで関連産業の
競争力強化・経済成⾧を実現し、くらし関連分野のGXを加速させることを目的とする事業
3.給湯省エネ2025事業
給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める
給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、
その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の
達成に寄与することを目的とする事業
4.賃貸集合給湯省エネ2025事業
賃貸集合給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める
給湯分野について、特に賃貸集合住宅に対する小型の省エネ型給湯器の導入支援を
行うことによりその普及拡大を図り、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の
達成に寄与することを目的とする事業
の4つとなります。
対象期間
・契約日の期間
工事を行う前に契約する必要があります
・交付申請期間
2025年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2025年12月31日まで)※1
※1締切は予算上限に応じて公表します。
補助額(補助上限)
子育てグリーン住宅支援事業なら
1戸当たりの住宅の省エネ性能に応じて
最大160万円
先進的窓リノベ2025事業なら
設置する製品の性能と大きさ、および設置する住宅の建て方に応じた、製品ごとの補助額(定額)の合計で
1戸当たり最大200万円
※補助申請については、1つの申請にあたりの合計補助額が5万円以上の工事のみ対象となります。
給湯省エネ2025事業なら
性能要件を満たした高効率給湯器に応じた定額を補助で
最大20万円
賃貸集合給湯省エネ2025事業なら
小型の省エネ型給湯器に応じた定額を、上限(1住戸1台まで)の範囲内で、台数を乗じた金額と
機器設置に伴う対象工事の一部負担で
1台当たり最大10万円
気になる方がいましたら
(有)Y&M企画工房ホームページ
お問い合わせよりご連絡下さい